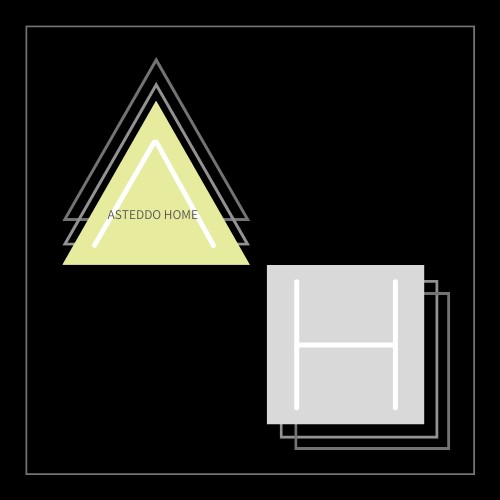こんにちは。
今回は耐震についてのお話しです。
家づくりを考える時に仕上げ材のこだわりも勿論大切ですが、住宅の基本性能として
気密や省エネ性、そして“耐震性能”という完成した後では工事が出来ない部分を十分に検討する必要があります。
耐震等級って?
耐震等級とは、地震に対する建物の強度を示す指標のひとつです。
住宅の性能を客観的に評価できる共通ルールとして『住宅性能表示制度』が定められました。
耐震等級は、この住宅性能表示制度の中の耐震性能に関する基準のひとつとなります。
耐震等級では地震に対する損傷防止と倒壊防止の観点から地震に対する倒壊のしにくさを耐震等級1~3の段階
に分けて示しています。
耐震等級の数字は大きい方が性能が高くなっています。
耐震等級1とは
耐震等級1とは建築基準法で定めれられた耐震基準と同程度で、次の通りです。
・数百年に一度程度発生する規模の地震による力(震度6強~7相当)に対して、倒壊・崩壊しない
・数十年に一度程度発生する規模の地震による力(震度5強相当)に対して、損傷を生じない
これから新築を建てる場合、最低でも耐震等級1を満たしてなければならない法律となっています。
耐震等級2とは
耐震等級2とは耐震等級1の1.25倍の耐震性があることを示します。内容は次の通りです。
・数百年に一度程度発生する規模の地震による力(震度6強~7相当)の1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しない
・数十年に一度程度発生する規模の地震による力(震度5強相当)の1.25倍の力に対して、損傷を生じない
災害時等で避難所となる学校などの公共施設は、耐震等級2の基準を満たすように定められています。
耐震等級3とは
耐震等級3とは耐震等級1の1.5倍の耐震性があることを示します。内容は次の通りです。
・数百年に一度程度発生する規模の地震による力(震度6強~7相当)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない
・数十年に一度程度発生する規模の地震による力(震度5強相当)の1.5倍の力に対して、損傷を生じない
耐震等級3は現行法では最高基準であり、警察署や消防署などは耐震等級3を満たすように設計されています。
耐震等級を高くするメリット4つ
①当然に耐震性が高くなり万一の地震の際にも甚大な被害になりにくい。
2016年に起きた熊本地震では、震度7の地震が立て続けに起きましたが、そのような中でも
耐震等級3を取得している建物は、大部分が被害を受けなかったことがわかっています。
②地震保険料が安くなる
耐震等級に応じて地震保険料の割引を受けることができます。
火災保険加入時にあわせて検討してください。
一般的に、
耐震等級3:割引率50%
耐震等級2:割引率30%
耐震等級1:割引率10%
年額で10~50%の割引は大きいですね。
③低金利で住宅ローンを借り入れできる(フラット35Sの場合)
長期優良住宅や省エネルギー性や耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合、
住宅ローン金利の引き下げ制度であるフラット35Sを利用することができます。
このほかにも、金融機関によっては独自に関する住宅ローンの金利引き下げを行っている場合が
あります。
④贈与税の税制特例がある
省エネ性、耐震性等に優れた住宅では、贈与税の非課税枠が拡大されます。